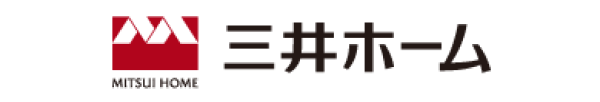マイホームを買う前に読んで安心Q&A㉚
マンション管理の課題(その1)
マイホームとして、新築または中古マンションを購入する方は少なくありません。国土交通省によれば、令和5年末までに我が国で分譲されたマンションは約700万戸です。一方、総務省の令和5年住宅・土地統計調査によれば、令和5年10月1日現在における我が国の住宅総数は約6千500万戸。住宅総数の1割以上は、今や分譲マンションとなります。横浜市や川崎市といった大都市を抱える神奈川県であれば、割合はさらに高くなるでしょう。
さて、マンションを購入する際に、みなさんは何を重視するのでしょうか。多くの場合は、立地、価格、間取り、日照・採光、耐震性、周辺環境、設備といったところでしょうか。マンション管理については、ほとんどの方が重視しない、というよりも、マンション管理は、管理費を払えば管理会社が適切にやってくれるもの、と考えている方が大半かと思われます。
実は、マンション管理には様々な課題があります。これらについても、知った上でマンションを購入されることをお勧めします。課題があるといっても、過度に恐れる必要はありません。ですが、無用なトラブルはやはり避けたいものです。知っておいて損はないはずです。
区分所有者は共同経営者
2001年に「マンション管理適正化法」が施行されました。適正なマンション管理の仕組みづくりを進める法律ですが、その背景には、マンションが様々な管理上の問題を抱えているという状況があります。
ここでは「建物の不具合」と「費用負担」から、管理の難しさについて考えてみます。建物や設備は使用によって劣化も進むため、一定程度の不具合が発生します。建設当初の水準にまで戻す「修繕工事」の費用は一般に高額で、マンションによっては費用負担が難しい場合もあります。修繕工事による現状維持ができないマンションは、管理不全に陥る可能性が高まります。
マンション管理の難しさは、現状維持だけでは市場価値を維持できない点にあります。何十年と快適に住み続けるには、建物や設備をグレードアップする「改良工事」も必要です。これを怠れば陳腐化が進み市場価値も低下します。
とはいえ、改良と修繕を合わせた「改修工事」には、さらに多額の費用が必要です。管理組合には、どのタイミングでどの程度の投資をするのが合理的か、という判断が求められます。この行為は「管理」というより「経営」と表現する方がふさわしいでしょう。
マンション管理が難しいのは、マンションの「経営」を区分所有者が「共同」で行う点です。委託管理であっても、合意形成や意思決定は区分所有者が担わなければなりません。
残念ながら、マンション管理を「共同経営」だと認識しているマンション購入者はかなり少ないようです。マンションの購入は、良好な居住環境と市場価値を維持するため、共同経営者になることと同義です。この認識を持ってマンションを購入することが、適正なマンション管理の第一歩といえます。
「2つの老い」が生む問題
いわゆる「築古マンション」であっても、ビンテージマンションなどと呼ばれるマンションでは、しっかりとした維持管理がなされている場合があり、それなりの価格で取引が売り出されています。一方で、住宅部分はピカピカに改修されていて、割安に感じられる価格で取引されているものもあります。いずれのマンションを買う場合でも、「2つの老い」が生む問題について、知っておくことは重要です。
マンション管理の業界では、いわゆる「築古マンション」を、高経年マンションと呼ぶことがあります。
高経年マンションでは、建物の老朽化と住民の高齢化という「2つの老い」が問題となっています。2つの老いは多くの場合、相互に悪影響を及ぼします。
建物の老朽化が進めば修繕費がかさみます。住民の高齢化が進み、年金で生活する人が増えれば、高額な修繕費の負担は難しくなります。「自分が死ぬまで住めれば…」と考える人が多くなれば、適切な修繕が行われず、管理がしっかりと行われていない「管理不全マンション」に陥りかねません。 最終的には「有害・危険マンション」となり、周辺住民や地域社会に多大な迷惑をかけます。
滋賀県野洲市では実際に、外壁や手すりが崩れ落ち、有害物質であるアスベストも露出した「有害・危険マンション」が発生し、社会問題となりました。市は区分所有者に改善を指導しましたが、最終的には行政代執行として強制的に解体する事態となりました。一部の区分所有者は、その費用を返還していません。市民の税金で解体することになったのです。
「高経年」の明確な定義はありません。国土交通省は築40年以上の分譲マンション数の推移を公表していますが、築40年は十分に高経年といえます。2024年の時点で築40年を超えるマンションは、特に注意が必要です。
理由の一つは、1981年の建築基準法改正前に確認申請した旧耐震基準のマンションが多く含まれている点です。大規模な地震があると、外壁や手すりが崩れ落ちる可能性が高く、耐震改修などの修繕費用も高額になります。
もうひとつは、1983年の改正前の区分所有法には、管理組合について明確な規定がなかった点です。当時の法律で分譲されたマンションの中には、現在でも管理組合活動が存在しないものや、一部の区分所有者による不公平な管理がなされているものがあります。
修繕積立金不足の構造的問題
マンションの管理不全は、「管理の機能不全」が建物の劣化や損傷の放置を引き起こしている状態を指します。管理の機能不全が起きる要因は多々ありますが、重要なものの1つが「修繕積立金の不足」です。
マンションでは、12年から18年の間に1度大規模修繕工事が行われます。その費用負担は戸あたり数百万円と高額で、全ての区分所有者が一度に支払うことは難しく、工事費用を積み立てるために数万円の「修繕積立金」を毎月各戸から徴収することが一般的です。
大規模修繕工事は、長期修繕計画という、30年以上の修繕計画に基づいて実施されます。この計画をみると、次の大規模修繕工事のために、どの時点で、どのぐらいの額が積み立てられていなければならないか(計画上の残高)が分かります。
国土交通省が令和5年に実施したマンション総合調査によれば、長期修繕計画で必要とされる積立金が不足しているマンションは、36.6%となっています。不足している、というのは、長期修繕計画上の残高より、実際の残高が少ない状況です。とはいえ、多少不足することはあり得ることで、その場合は銀行等から借り入れることで凌いでいきます。しかし、大幅に不足すると、必要な大規模修繕工事を行うことができなくなる可能性が高まります。
修繕積立金が不足する要因には以下のものがあります。1つめは、震災や関係者の不正使用などの事故に起因するもの。2つめは、賃貸利用が多いマンションで需要が低迷し、家賃の減少によって滞納が増加するもの。3つめは、修繕積立金徴収額が値上がりし、多くの区分所有者が負担できない状態です。これらは、は今後どのマンションでも起こり得ます。
国土交通省が公表する長期修繕計画のガイドラインでは、長期修繕計画の計画期間を 「30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上」としています。給排水管、エレベーター、機械式駐車場などは耐用年数が30年以上の場合が多く、3回目の工事費用が1回目の倍以上になることもあります。
最初の長期修繕計画は分譲業者が作成しますが、計画期間が30年で3回目の工事を考慮していなければ、設定された徴収額では3回目の費用を賄えません。どこかの時点で計画を見直し、3回目を含めた計画に基づいて徴収額を値上げする必要があります。
新築マンションの多くは、修繕積立金徴収額が段階的に値上がりする「段階増額積立方式」で設定しています。当初の徴収額は低く抑え、築20年を超えたころに、当初の倍以上への値上げを予定しているケースがこれまで多くみられました。さらに3回目を視野に計画を見直すと、工事費高騰などの影響で想定外の値上げが必要となることもあります。
値上げに対応できない区分所有者が多ければ、「修繕積立金の不足」に陥ります。3回目の工事が近づくころには、区分所有者の高齢化も進み、負担を難しくする要因となります。
ご不明な点がございましたら、明海大学不動産学部までご確認ください。
明海大学不動産学部教授 小杉 学