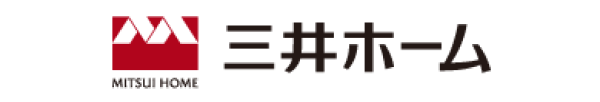マイホームを買う前に読んで安心Q&A㉛
マンション管理の課題(その2)
前回に引き続き、新築または中古マンションを購入する前に知っておきたい、マンション管理の課題についてお話します。今回は、管理会社と第三者管理(管理業者管理者方式)についてです。前回同様、マンション管理に課題があるといっても、過度に恐れる必要はありません。
管理会社への過大な期待
国土交通省の令和5年度マンション総合調査によれば、約73%の管理組合がマンション管理業者に管理を「全部委託」しています。この言葉の響きは「管理会社が全部行ってくれる」という誤解と過大な期待を招きがちです。
マンション管理適正化法では、一定の条件を満たし国交省に登録された「マンション管理業者」でなければ、全部委託を受託できないと定めています。
当然ですが、管理業者が行うのは管理組合と締結した契約書に記載された業務だけです。同調査によれば、管理を委託する管理組合の約94%が、同省が示している管理委託契約の標準的な指針(標準契約書)に、「おおむね準拠」した内容で契約しています。標準契約書で定める委託業務は①事務管理業務、②管理員業務、③清掃業務、④建物・設備等管理業務の4つです。この4業務全てを委託するのが全部委託です。
全部委託であっても、管理業者は契約書に記載されていない業務は行いません。例えば①の事務管理業務には、管理組合の会計や出納、理事会や総会の運営などの重要な業務が含まれますが、予算案や決算案の「素案」作成や、理事会や総会運営の「支援」に留まります。作成や運営そのものは、あくまで管理組合が主体的に行う業務です。また、長期修繕計画の作成や大規模修繕工事の実施は、標準契約書には含まれません。管理業者または他の専門業者などと別途契約する必要があります。
標準契約書は管理業者がマンション管理の知識や技術に乏しい管理組合を自在に操り、不当に利益を得ることを防ぐのが目的です。しかし、その内容は素人には極めて分かりにくいものです。このため、別の問題も生じています。
契約内容を理解しない区分所有者が、管理業者に契約外の業務や無理難題を要求し、これらがエスカレートしたカスタマーハラスメントが相次いでいるのです。23年の標準契約書の改訂では、これに対応する条項も盛り込まれました。区分所有者は管理業者に委託している業務と、管理組合が担う業務の違いを正確に理解する必要があります。
過度な依存が生む悲劇
マンションを適切に管理する上で、管理業者は欠かすことができない存在です。しかし、管理業者に不満を感じている管理組合も一定割合存在します。
国土交通省の令和5年度マンション総合調査では、管理組合の約24.5%が管理業者を変更していました。筆者らの調査で管理業者への不満として挙げられるのは、①不要不急の工事提案、②不当に高額な工事費用③高額な委託費などです。こうした不満は業者側も認識しています。
この状況が生まれた一因は、近年まで管理業者が弱い立場に置かれていたことでしょう。
管理業者は価格競争で管理戸数の拡大を狙います。契約解除と業者変更を避けるため、委託費値下げや契約外業務の要求をサービスとして受け入れてきたのです。
この時代に、「やってもらって当たり前」という考えが多くの管理組合に定着し、管理業者に過度に依存する体質ができました。その結果、理事会や総会で管理業者が準備した議案が検討もされず採択されるなど、管理組合の主体性が失われたのです。
一方、委託費の値下げで利益が得られなくなった管理業者は、大規模修繕工事の受注で利益を確保しようと考えます。主体性が失われた依存体質の管理組合が利益収奪の「カモ」となる問題も起きました。
しかし現在では、人手不足、人件費の高騰、高経年マンション管理の難しさを理由に、管理業者が委託費の値上げを提示し、委託外業務も断るようになりました。採算があわない、またはカスタマーハラスメントが常態化している管理組合に対しては、管理業者から契約解除するケースもみられます。そうした管理組合は、他の業者との委託契約も難しく、かつての状況とは一変しているのです。
過度な依存体質のまま委託費の値上げに応じない管理組合は、管理業者から見放され路頭に迷います。管理組合と管理業者の関係は、BtoB(企業間取引)と認識すべきです。管理組合は「やってもらって当たり前」との考えを捨て、経営者として対等な立場を築く努力をしなければ生き抜けないのです。
急速に拡大する第三者管理
現在、管理組合の多くは理事会方式で運営されています。区分所有法が定める「管理者」は、全ての区分所有者の代理として管理を執行する管理組合の最高責任者です。理事会方式では、区分所有者から選ばれた理事が理事会を組織し、理事の中から選ばれた理事長が管理者となります。
これに対し、管理者や理事、監事を外部の専門家が担うのが第三者管理方式(外部管理者方式)です。管理不全やその兆候を示すマンションの管理者や理事などに、マンション管理士といった専門家が就任し、管理組合を再生させる取り組みが十数年前からみられるようになりました。
国土交通省は2017年に第三者管理に関するガイドラインを整備しました。その内容は、理事会存続型の第三者管理が対象でした。しかし、現実には理事会廃止型も行われ、「区分所有者は理事を担う煩わしさから解放され、関与する専門家も理事会の議論に付き合う手間が省ける」という認識が広がりました。
そのころから、区分所有者が高齢化し理事の担い手不足が問題となりました。さらに、タワーや高級マンションでは、設備が高度化・複雑化しました。
こうした状況で拡大したのが、第三者管理方式(外部管理者方式)の中でも、理事会を設置せずに管理業者自らが管理者に就任する「管理業者管理者方式」です。この方式は、一部の投資用単身居住者向けマンションで行われていたもので、対応する標準管理規約やガイドラインなどはありませんが、ファミリー向け一般マンションにも急速に拡大しました。
その結果、同方式を採用する管理組合の一部では、理事会不在がもたらす管理者(管理者を受託する管理業者)の独断専横的行為が生じるようになりました。また、管理委託や工事発注を行う立場の管理者と、受託者・受注者である管理業者が同一となることで、管理組合が不利益を被るような深刻な問題も起きています。
2024年6月7日、国土交通省は同方式に関するガイドラインを公表しました。それでも、管理業者管理者方式では、管理業者がコストも含めた管理内容の主導権を握ります。安定した管理が期待できる一方で、区分所有者はより主体的に管理業者を監督することが強く望まれます。
理事会を設置しない選択
「管理業者管理者方式」は、一般の新築・既存マンションにも急速に普及しています。しかし、その仕組みは難解で、様々な問題が発生する要因にもなっています。同方式はその名の通り、管理を受託する管理業者が管理組合の管理者(全区分所有者の代理人)も担います。すなわち、管理業者(管理者)が自らに管理を委託する形になります。
これは民法が無効と定める「自己契約」に該当しますが、本人が許諾した場合は有効です。マンションの場合、総会で十分な説明のうえで承認を得れば有効と解されます。また、管理業者(管理者)が自らと利害関係のある関連会社に大規模修繕工事を発注することがあります。これも民法が無効とする「利益相反取引」に該当しますが、こちらも総会承認があれば有効と解されます。
同方式では理事会が設置されません。そのため、管理者(管理業者)は独断で総会議案を作成し総会に諮ることができます。区分所有者の管理に対する主体性が育まれる機会もありません。総会では管理業者が作成した議案が、検討されないまま承認されかねません。仮に反対者がいても、反対の仲間を増やす機会やつながりもありません。
国土交通省が2024年6月7日に公表した同方式に関するガイドラインは、上記の問題点に対応し、アンケートの導入や修繕委員会の設置による独断専横的行為の排除、区分所有者や外部の専門家が担う監事による利益相反取引の監視強化など、充実した内容になっています。
とはいえ、多くの場合、同方式の選択は管理の煩わしさからの解放を望んだためです。理事会が無い分だけ修繕委員会や監事の責任と負担は増えます。これを担おうとする人がいるかは疑問です。
同方式では、管理業者が管理の主導権を握る構造になっています。理事の担い手不足が解消し、管理の煩わしさから解放される分、区分所有者の管理意欲が低下しやすくなります。その状況下で、理事会方式以上に積極的な監督が求められるわけで、この方式を採用するマンションの購入には、十分ご注意ください。
ご不明な点がございましたら、明海大学不動産学部までご確認ください。
明海大学不動産学部教授 小杉 学