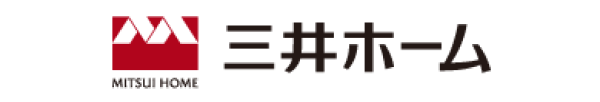マイホームを買う前に読んで安心Q&A㉞
都市計画マスタープランを読んでみよう
Q:自分のマイホームのある街の将来の姿がどうなっていくのか知りたいとき、何をみたらいいですか?
A:自治体の定める都市計画マスタープランを読んでみましょう。
個人的なことになるが、これまで持ち家とは縁がなく、借家住まいで暮らしてきた。マイホームを買う、ということは、どこかに住む場所を決めることである。その点では、借家を選ぶことと重なるところはあるだろう。建築学を学んだり、都市計画学の分野で研究をしたりしているのだから、自分が住む場所について、じっくり考えて論理的に選びたいものだが、実際には、突発的な必要性から慌てて選んでばかりで、専門的な知識の出番があまりなかった(あるいは使いこなせなかったか)。このような事情から、ここでは、確固たる経験ではなく、できるならば、このように住む場所を選びたいという、願望に近い話を書かせていただく。
そういうわけで、自分が住む場所が将来どうなるのか、ということを知りたい場合には、その街のある自治体の都市計画マスタープランを読むのがよい。最初に、断っておくと、これができるのは、自分が住む(住もうと思っている)場所の自治体が都市計画マスタープランを作成している場合である。ただ、神奈川県では多くの自治体が都市計画マスタープランを策定しているので、たいていの場合読むことができるだろう。自治体のHPの検索で「都市計画マスタープラン」と検索してみよう。
街の将来の何を気にするか、人によって異なる。でも多くの人が、マイホームのある場所に求めることは、日当たりや利便施設や、静かな環境など、居住性や資産性にかかわる様々な要素が良い状態に保たれることだろう。都市計画では、それを土地利用、交通、緑という物的要素とその状態からとらえる。都市計画マスタープランは、都市計画法において市町村が定めることができる「都市計画に関する基本的な方針」と位置付けられている。字面から、堅苦しいイメージをもつかもしれない。しかし各自治体が、住民の意見を取り入れながら、また読み手も住民であることを意識してまとめていることから、読み易い文書になっている。ただ、ページ数は多いので、読み通すのには少し時間がいる。通常、概要版もまとめられているので、そちらから読んで、気になるところを詳細版で読んでみるのもいいだろう。
自分が住む、住もういう場所が、マスタープランの中で市町村内のどんな特徴をもった地域に入っているかをまず見てみよう。同じ住宅地であっても、戸建てが中心であるのか、マンションが多いのか、商業や業務用途の建物が少し混ざっているのかなど違いがある。このような土地利用の現況の分析が示されている。また地域の課題や懸念材料などが書かれている。開発当初のゆったりした戸建て住宅が細分化されていくことや、震災時の避難路の心配や、豪雨に際しての浸水の心配などが取り上げられている。マスタープランの文書の特徴は、たんたんと、簡潔に書かれていることである。しかし、書かれているということは、それが確実な事実だというのが重要なところである。行政、策定に参加した住民、学識経験者などが何度も読み返してまとまった文書であるだけに、根拠のない思い込みで書かれたような部分はない。一言書いてあれば、確実に何かある、と思って受け止める必要がある。
交通や緑地についてもそれぞれに項目がとられている。交通の事項では、渋滞の問題になっている交差点や、それを解消すべく計画されている道路、また新規の公共交通路線、逆に維持が難しくなっているバス路線の状況などがまとめられている。緑地や環境の事項では自然の緑地、農業用地の状況や公園の多寡の状況、公園の偏在などの状況が説明されている。自分の住む場所が大都市の都心近くであれば、業務中心地の分析も気になるところだろう。
このような各論での状況分析を踏まえて、地域ごとの計画の方針が示されるというのがマスタープランの章立ての構成の典型である。残念ながら、未来の街の分かり易い絵はマスタープランでは期待できない。その代わりに、地図と図式と簡潔な言葉で、市町村内の各地区の将来に向けての方針が示される。ここでも、将来の街の姿の説明は、表現が抑えられている。そのため、よそ者が初めて読むのでは、街がどのように変わっていくのかはっきりはつかめないかもしれない。しかしそこに書かれているのは、市町村の将来を考えたときに関係する人たち(住民、行政、計画策定に関わった専門家など)皆が、受け入れることができる、できればそうなってほしい街の姿を言い表した言葉、図である。現状分析で懸念されることが実現してしまうのか、そうなってほしい将来像が実現するのかは、時間が経たないとわからないが、自治体が課題を認識し手立てを講じていることを確認することは、街の将来の姿がどうなっていくのか知ることに他ならない。
慌てて住む場所を選ばざるを得ない時には、使いこなすのが大変な情報かもしれない。しかし、マイホームを買うという大きな選択に際しては、読む価値がある情報だと思う。自分は、これまでそういうことに縁がなかったが、老後の住宅は、住みたい場所のある自治体のマスタープランも読んでじっくり選んでみたい。
ご不明な点がございましたら、明海大学不動産学部までご確認ください。
明海大学不動産学部教授 齋藤 千尋